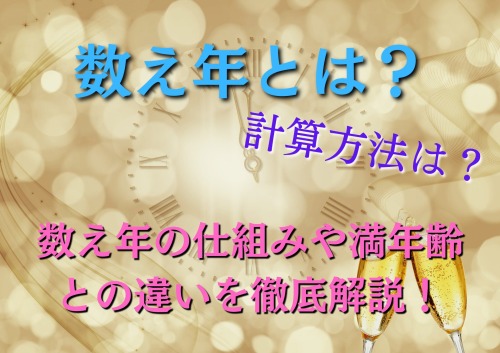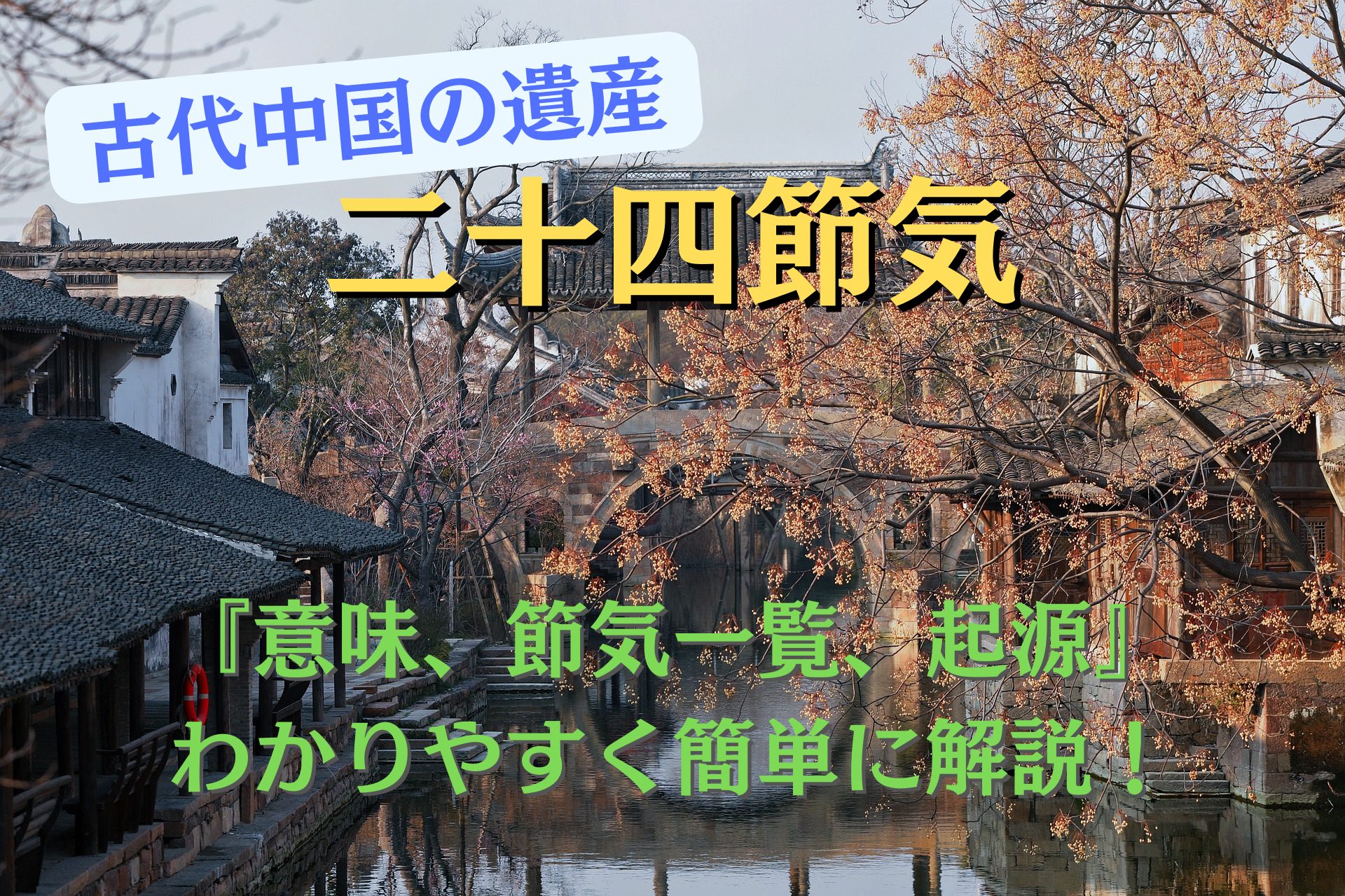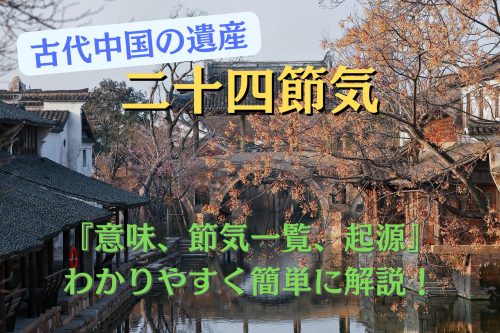考える人
考える人24節気って聞いたことはあるけど、一体なんだろう?
 悩む人
悩む人天気予報でよく「明日は立春。暦のうえでは明日から春です!」とか言うよね。
二十四節気って「なんか聞いたことはあるけど、細かく気にしたことはない」って感じですよね。
でも四季が豊かな日本では特に大切な概念でもあります。
今回は「二十四節気をそもそも知らない人」から「聞いたことはあるけど、細かくは知らない人」まで役立つ、「二十四節気の意味」や「二十四節気の起源」などを紹介していきます。
それでは早速>>>
- 二十四節気の意味
- 二十四節気の起源
- 二十四節気一覧
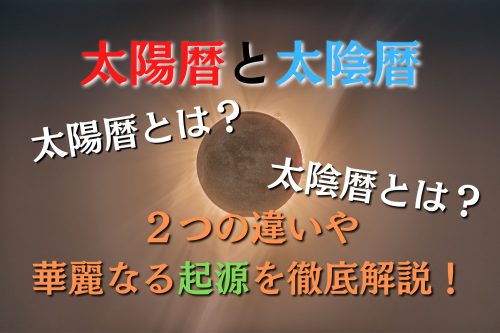
二十四節気とは?

二十四節気とは簡単にまとめると季節の区分です。
皆さんもご存知の通り、季節には春、夏、秋、冬がありますよね。
二十四節気ではこれらをより細かく区分し、各季節をさらに6つずつ分けます。
- 春×6区分
- 夏×6区分
- 秋×6区分
- 冬×6区分
つまり、4(春夏秋冬)×6区分=24区分になるので「二十四」節気となります。
古くは自給自足で生活するために、季節をより細かく把握するのが非常に重要な指標でした。
寒いと穀物が育ちにくかったり、その逆もしかりですからね。
言うならば、より実際の季節に合わせるための正確な区分です。
二十四節気の起源

二十四節気は古代中国で考案されました。
その起源は中国の春秋戦国時代にまで遡ると言われています。
中国の春秋戦国時代っていつ?って話ですよね。
春秋戦国時代は紀元前770年〜紀元前210年頃までです。
現在を西暦2000年と考えると、およそ2000〜3000年前。
びっくりですね。
中国ではこんな古代から季節を考え生活に活かしていたと考えるととんでもなくすごいことですよね。
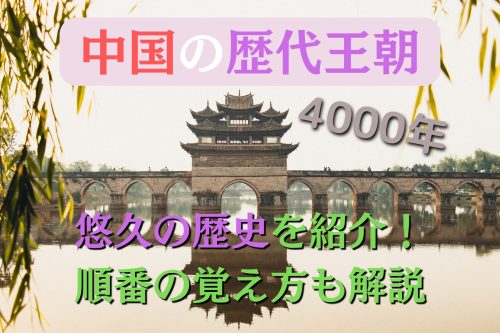
日本ではいつから二十四節気が使われているのか
中国ではおよそ2000〜3000年前の古代春秋戦国時代でしたね。
では、いつから日本でも二十四節気は使われるようになったのでしょうか?
答えは奈良時代〜平安時代です。
- 奈良時代は西暦700年頃=(およそ1300年前)
- 平安時代は西暦800年頃=(およそ1200年前)
結構前ではありますが、古代中国の春秋戦国時代がおよそ2000〜3000年前なので二十四節気は大体1000年ほど遅れて入ってきた事になります。
そう考えると古代中国の文明がいかに先進的だったか分かりますね。
日本の季節とのズレ
 喜ぶ人
喜ぶ人暦のうえでは今日から「春」です!
おそらく皆さんも天気予報を見ていてこんなセリフを聞いたことがあるんじゃないでしょうか?
しかし、実態は春なのに凍えるほど寒い。
天気予報士がこのセリフを言うときは決まって全く季節と合ってないんですよね。
暦は春なのに季節は冬真っ只中などの現象が起きるのには理由があります。
非常に単純ですが、二十四節気は中国生まれだからです。
中国の中でも中原(黄河流域)で誕生したとされています。
今で言う河南省の辺りですね。
中原(黄河流域)の位置

中原のおおよその位置を示しました。
ご覧の通り日本が右側の方に見えています。
そして中国の中原は日本より結構西の方にありますよね。
このように二十四節気は中国を基準としており、日本よりも季節が先に進んでいます。
なので日本はまだ冬なのに、暦は春などと言ったズレが発生します。
二十四節気の一覧と日付

ここからは二十四節気の一覧とおおよその日付を見ていきましょう。
なぜ「おおよその日付」と言ったかというと、二十四節気は旧暦を元に作れられているため、今現在世界中で使われている新暦とはズレが発生するからです。
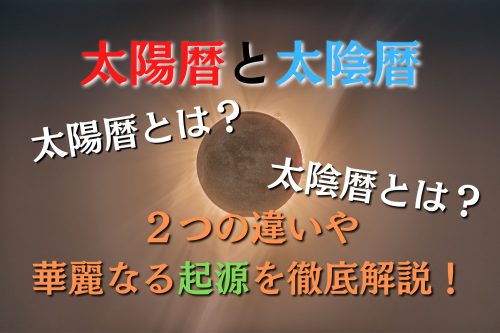
では話を戻して二十四節気の一覧を見ていきましょう。
春の二十四節気
| 節気名 | 新暦での日付 |
|---|---|
| 立春(りっしゅん) | 2月4日頃 |
| 雨水(うすい) | 2月19日頃 |
| 啓蟄(けいちつ) | 3月6日頃 |
| 春分(しゅんぶん) | 3月21日頃 |
| 清明(せいめい) | 4月5日頃 |
| 穀雨(こくう) | 4月20日頃 |
立春
旧暦ではこの頃がお正月。
そのため、立春は春の始まりであり1年の始まりでもあります。
また、立春から春分辺りの間に吹く強い南風を「春一番」と言います。
春分
日々過ごしている中で実は昼と夜の長さが違うことをご存知ですか?
ですが、昼と夜の長さが等しくなるのが1年にたった2回だけあります。
その2回の内の1回がこの春分です。
もう一回は秋分。
夏の二十四節気
| 節気名 | 新暦での日付 |
|---|---|
| 立夏(りっか) | 5月5日頃 |
| 小満(しょうまん) | 5月21日頃 |
| 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日頃 |
| 夏至(げし) | 6月21日頃 |
| 小暑(しょうしょ) | 7月7日頃 |
| 大暑(たいしょ) | 7月23日頃 |
夏至
1年の中で太陽が最も長い時間照らす1日。
つまり、最もお昼が長い1日となります。
ちなみにこれは地球の北半球でのお話。
北半球に属する日本では例の通り、1年でお昼が一番長い1日となります。
ですが、季節が真逆の南半球に属するオーストラリアなどでは1年で最もお昼が短い1日となります。
※南半球でお昼が最も長くなる日は後ほど解説
秋の二十四節気
| 節気名 | 新暦での日付 |
|---|---|
| 立秋(りっしゅう) | 8月7日頃 |
| 処暑(しょしょ) | 8月23日頃 |
| 白露(はくろ) | 9月8日頃 |
| 秋分(しゅうぶん) | 9月23日頃 |
| 寒露(かんろ) | 10月8日頃 |
| 霜降(そうこう) | 10月23日頃 |
立秋
暦のうえで秋が始まる日。
8月7日頃を指すので日本では丁度灼熱の時期ですね。
ですが暦上は秋です。
秋分
1年で2回、昼と夜の長さが等しくなる1日。
2回の内の秋の方。もう1回は春の春分。
冬の二十四節気
| 節気名 | 新暦での日付 |
|---|---|
| 立冬(りっとう) | 11月7日頃 |
| 小雪(しょうせつ) | 11月22日頃 |
| 大雪(たいせつ) | 12月7日頃 |
| 冬至(とうじ) | 12月22日頃 |
| 小寒(しょうかん) | 1月6日頃 |
| 大寒(だいかん) | 1月20日頃 |
立冬
暦のうえで冬がスタートする日。
11月7日頃なので、日本はまだ秋と言ったところ。
冬至
1年の中で月が最も長い時間輝く1日。
つまり、1年で最も夜が長い1日。
ただしこれは日本など北半球に属する地域でのお話。
南半球のオーストラリアなどでは逆に1年の中で最もお昼が長い1日となります。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
最後のまとめです。
二十四節気とは?
二十四節気とは季節の区分。
春、夏、秋、冬、それぞれの季節をさらに6区分ずつ分けたもの。
二十四節気の起源
二十四節気は古代中国、春秋戦国時代に中原(黄河流域)で考案されました。
そのため日本の季節とは一定のズレが発生します。
何となく聞いたことはある二十四節気について少し理解が深まりましたか?
筆者はこんなに古いルーツを持っている驚きとともに何かロマンも感じます。笑
話が逸れそうなので今回はこの辺りで。
それではまた!